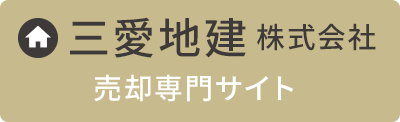瑕疵担保責任から契約不適合責任に法律改正
不動産を売るにあたって法律の改正が行われました。特に契約不適合責任につきましては売主に関係しますので押さえておくべきところでしょう。今回の民法改正により変更された内容を確認してみましょう。

2020年4月の民法改正により瑕疵担保責任から契約不適合責任へと名称が変わりました、内容も変更されました。どのように変更されたのかをしってもらうために説明いたします。
瑕疵の意味は
不動産取引上での瑕疵とは、欠陥品や不具合のことをいいます。
瑕疵とは本来の機能や性能がじゃない状態で、瑕疵と言われる例としては以下の状態が当てはまります。
雨漏りしている
屋根や壁から、室内に雨水等が入ってくる状態です。
シロアリの被害
木造の建物に発生します。シロアリが発生すると建物の強度が下がるのと見えない場所にあるのでトラブルになりやすいです。
地中埋設物
解体した時に土地の中から住宅の基礎部分や擁壁、昔使ってた井戸、使わなくなった浄化槽などが出てくる時があります。相続などでもらった不動産は過去のいきさつとかを知らないことが多いので出てきて売主もびっくりします。
事故物件などの心理的瑕疵
自殺や事件などの心理的瑕疵は事前に買い主へ通知する義務があるため、言わなくて売ったら瑕疵に含まれます。
瑕疵担保責任にはいくつかのポイントがあります。
隠れた瑕疵であること
(旧)瑕疵担保責任では隠れた瑕疵のときのみ、売主は買主に対して責任を負います。隠れた瑕疵とは、売主が告知した時に知らなかったり、気づかなかった瑕疵という意味です。つまり、売り主がシロアリや地中埋蔵物のことを知らなかったら、買い主は売り主に対して請求できませんでした。したがって、売り主がその瑕疵について知っていたかどうかが、重要になります。
請求できるのは「損害賠償請求」「契約解除」のみ
不動産の欠陥や不具合を売り主が知っていた場合、買い主にできることは「損害賠償請求」「契約解除」のいずれかのみでした。契約不適合責任ではより多くの請求ができるようになりました。
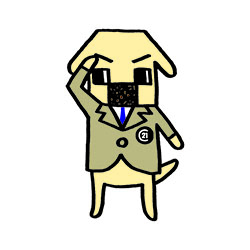
2020年4月の民法改正による変更点
2020年4月の民法改正でどのように変わったのか、変更点を見ていきましょう。主な変更点は次の4つです。
隠れた瑕疵であるかは関係なくなった
以前のように売り主が知っていたかいないかは関係なく、契約内容に適合しているかが論点です。契約内容に適合していなければ、売り主がすべての責任を負います。
売り主の責任範囲が拡大している
(旧)「瑕疵担保責任」では「契約締結時までの瑕疵」でした。「契約不適合責任」では「物件の引き渡しまでの瑕疵」です。売り主の瑕疵に対する責任の期間が長くなり、その分売り主の責任が重くなっているといえます。
買い主はより多くの権利が与えられている
(旧)「瑕疵担保責任」では買い主ができたことは「損害賠償請求」「契約解除」のいずれかでした。「契約不適合責任」では買い主の権利が追加されています。追加分も含めた、買い主の権利は次の5つです。
- 追完請求権:契約に沿った対応を請求する権利
- 代金減額請求権:売買代金の減額を請求する権利
- 催告解除:追完請求に応じない売り主に対し契約解除する権利
- 無催告解除:契約不適合を理由に契約解除を請求する権利
- 損害賠償請求:損害に対して補償を求める権利
損害賠償の範囲も拡大している
損害賠償請求は(旧)「瑕疵担保責任」でもできましたが、「契約不適合責任」では範囲が拡大しています。また、以前は信頼利益に限定されていましたが、履行利益も損害賠償請求の範囲内となりました。
例えば、雨漏りでホテルに寝泊まりしなくてはいけなくなった場合、「契約不適合責任」ではその宿泊費用も損害賠償請求の範囲に含まれます。
古い建物は契約不適合となる可能性が高いので、責任を追求されないように対処が必要です。ただし、物件の状態によって対処方法は異なりますから、自己判断はせずまずは不動産業者に相談することをおすすめします。
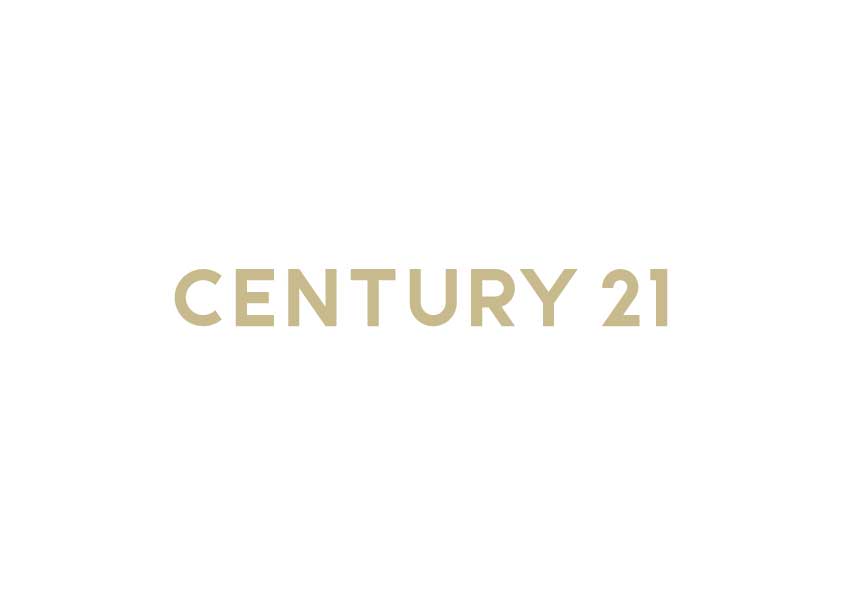
糸島市で不動産売却をご検討中の方は信頼と実績のあなたの街の不動産会社センチュリー21三愛地建へ
2020年4月の民法改正により、中古物件の売却は厳しくなりました。古くなった建物は解体し更地にして売却するなどなどの対策が必要です。センチュリー21三愛地建ではお客様に最適な売却方法をご提案いたします。糸島市で不動産売却をご検討中の方はお気軽にご相談ください。